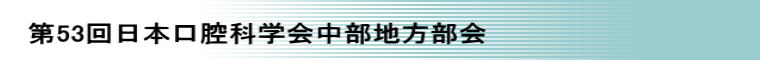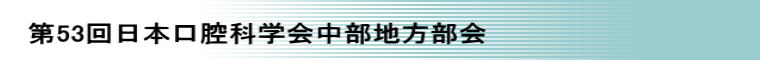|
|
| 特別演題 |
| ――――特別講演―――― |
戸塚靖則先生(北海道大学大学院 口腔顎顔面外科学 教授)
「これからの歯科医療,口腔外科医療を担う若き医療人へのメッセージ
−リーズナブルに考える−」
昭和48年に北海道大学歯学部を卒業後、これまで約40年間、千葉県がんセンターおよび北海道大学歯学部・同附属病院において、口腔癌や顎関節症、良性腫瘍、嚢胞、外傷・骨折、インプラントの診療に携わってきました。また、研究面では、がんに関連した基礎的・臨床的研究や、顎関節症に関する臨床的研究を行ってきました。しかし、最近10年間は、歯学部や大学院歯学研究科、北海道大学病院の運営、ならびに日本口腔科学会や日本口腔外科学会など、関連学会の理事会や委員会の活動等に時間を費やされることが多く、臨床も研究も過去の人になってしまっております。今回、第53回日本口腔科学会中部地方部会会長の野口 誠先生のご厚意により、講演の機会を与えていただきましたが、上述の理由で、講演のための新規の材料を持ち合わせておりません。そこで、これまで、私が口腔外科医として、また大学に籍を置く医療人として考えてきたこと、感じてきたことの一旦をお話しさせていただきます。
一言で言えば「リーズナブルに考える」ということになりますが、具体的な事例がないと話しが脱線してしまいますので、私がこれまでに行ってきた口腔癌の手術や口腔癌の顎骨浸潤などを材料にして、手術や研究、論文作成などについて、日頃考えていることをお話しする予定です。また、時間が許せば、顎骨骨折の治療やエナメル上皮腫の治療、さらにインプラント治療についてもお話ししたいと思います。
|
| |
| ――――教育講演―――― |
笹原正清先生(富山大学大学院 病態病理学 教授)
「PDGFの病態生理学 〜発生生物学から臨床医学へ〜」
血小板由来増殖因子(PDGF)は間葉系細胞の強力な増殖因子である。PDGF-AA、AB、BB、CC、DDからなるligandと、受容体(PDGFR)-αα、αβ、ββが同定されている。それぞれが個体発生や器官形成に必須であるが、近年、PDGFの病態生理学的な研究が活発に展開されている。PDGFは腫瘍、線維症などの種々の病態発生に関与し、治療の分子標的として注目される。また、PDGFの投与による歯周病や難治性潰瘍治療の試みも進行中である。PDGFの抑制が骨粗鬆症や耐糖能を改善することを示す臨床報告もあり、全く新しいPDGF機能も示唆されつつある。しかしながら、生後にも脳を含む全身の広い範囲に発現するPDGFの生理的な機能は不明である。PDGF特異的な阻害薬物がないこと、PDGFのnull
knockout(KO)マウスが周産期の前後で死亡することなどが原因である。近年、我々の研究室でPDGFR-β遺伝子KOが細胞種あるいは発達の時期特異的に誘導できるモデルマウスを開発した。新しい手法により開始したPDGF機能解析の研究の一旦を紹介し、病態生理学におけるPDGFの役割を考察したい。
|
|
|