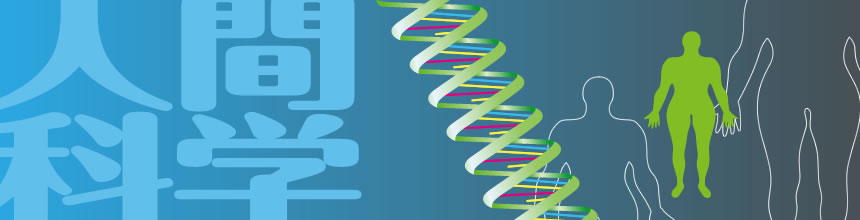
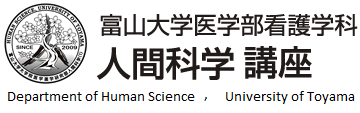
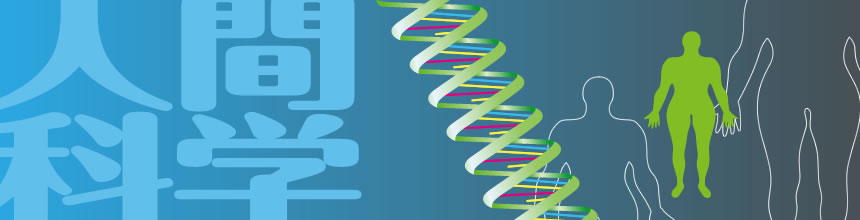
大学院で看護学を学ぶということはどのような位置付けでしょうか?それは学部教育に比べて、何かがプラスαされていなければなりません。
将来の看護教育の中心に立つ人にとって、より高い看護実践能力を学ぶということはもちろん必要です。しかし、そればかりではなく、私は看護学の向上のため医学実験研究の経験、看護学のみならず健康科学にも視点を向けること、国際感覚を身につけるための英語力の向上ならびにリーダーシップを発揮できるための社会感覚(コミュニケーションを含む)などが必要と考えています。特に大学院教育の中でしか経験できない実験研究の考え方は生涯においてきっと役に立つでしょう。
実験研究は科学であり、そこには再現性、普遍性というものが存在します。一方、看護学は臨床実学であり、人間が相手である以上、かならず例外があり、相手に即して考えていかなければいけないことは周知の事実です。両者は一見異なるように見えるのですが、実は車の両輪と言えるのではないでしょうか?様々な患者様に対し、看護師として何がプラスできるか?これを養うことが目的になります。
看護の中に自分らしさを築くには、ケース・バイ・ケースの実例の中からいかに共通項を見つけて体系化していくかが重要ではないかと考えます。「看護の中の準不変性の発見」とでも名付けたら良いでしょうか。このことが理解でき実感できた人とできなかった人において、その満足度の差はきっと大きいのではないかと推測するのですが、いかがでしょうか。
単に学位というタイトルの取得にこだわるのではなく、看護学の中に研究の面白さを見つけて下さい。現代社会の難局を乗り越えるには、ガッツ、多様性の理解、研究者育成の3つが必要と考えています。