09:女性医学チーム「女性医学」×「?」
コラボレーションぞくぞく。
座談会メンバー
-
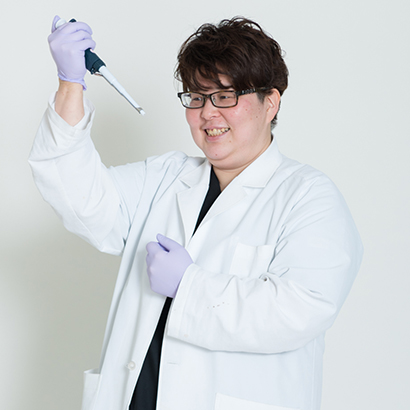
鮫島梓
PROFILE PROFILE
PROFILE鮫島梓
- 役職
- 助教
- 出身大学
- 富山大学
- 入局年
- 2009年
- 研究テーマ
- エストロゲンと糖代謝
- 専門医 等
- 日本産婦人科学会 産婦人科専門医、女性のヘルスケアアドバイザー、障害スポーツ医
-
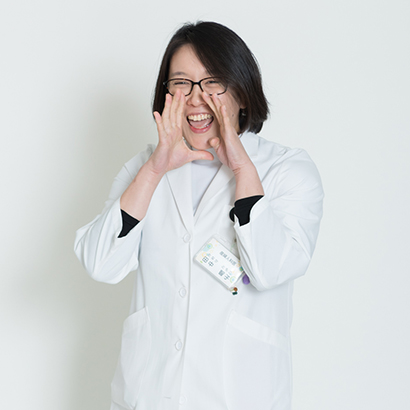
田中智子
PROFILE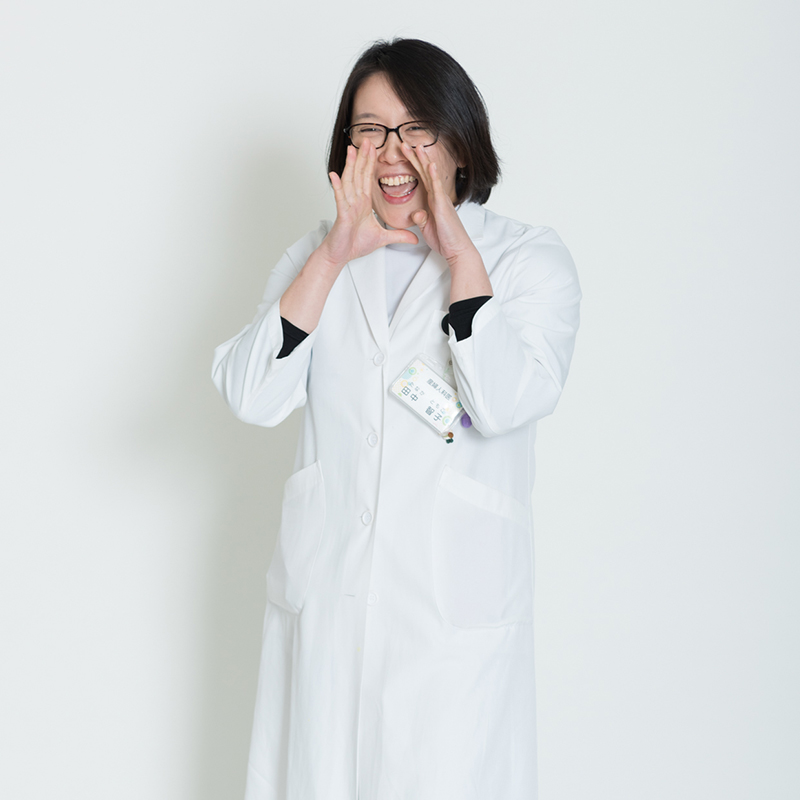 PROFILE
PROFILE田中智子
- 役職
- 医員
- 出身大学
- 富山大学
- 入局年
- 2010年
- 研究テーマ
- 女性医学
- 専門医 等
- 日本産婦人科学会専門医
もう、この研究無理かも、と思っていました。1週間前は。
ーおふたりは、なぜ大学院へ?
鮫島:今は、ルールの制限があったり、やれることが限られてしまったり。決まったことしかやらないから、言い方はちょっと悪いですけど、臨床だけだと飽きてきちゃう。そういう時に大学院で研究すると、臨床をやる時も見方が変わったりするんですよ。
田中:社会人でありながら学生気分を味わえるのも特権ですよね。ちなみに、私は今まさに、学生の身分です(笑)。
鮫島:私服で過ごす時間が増えたり、急患で呼ばれることがなかったり。ただただ、働いている毎日からちょっと気分が変わるから、大学院はいいと思う。
田中:研究は大変ですけど。
鮫島:私がやっていた研究を、ちょうど田中先生に引き継いでるんですけど。今ちょうど大変な時期だよね?
田中:はい(笑)。更年期の女性における代謝異常、糖尿病について研究しているんですけど、なかなか思うような結果が出なくて。
鮫島:糖代謝異常と一口に言っても、エストロゲンがどこに働いているかは、わからないんですよね。脂肪なのか、肝臓なのか。糖尿病の一つの病態として、脂肪組織での炎症があるんですが、その中でも制御性T細胞の役割を研究していたんです。ただ、なかなか思うような結果を出せず。そのあと、田中先生にバトンタッチしまして。
田中:閉経だとうまく結果が出ないので、今は妊娠糖尿病で実験しようとしているところ。妊娠すると耐糖能異常って言って、糖尿病みたいな状態になるんですね。それが妊娠糖尿病の症状なんですけど。この症状のマウスを使って、高エストロゲン状態で免疫細胞が変化するかどうか、免疫の変化によって糖代謝になりやすいかどうか、という研究をしています。今はようやく、結果がだいたい揃ってきて、次の免疫系の細胞を見ようというところ。
鮫島:この対談が1週間前だったら、そうもいかなかったよね。
田中:本当にそうですね。先週の時点では、結果は出揃ったものの、次の手がかりが見つからず。もうやめようかと思っています、と答えていたかもしれない(笑)。
鮫島:でも、今は光が見えてきた感じ?
田中:一緒に研究している薬学部の先生や、鮫島先生と意見交換をして、次に何をすれば免疫系の状態が変わるかヒントをいただいたので。
鮫島:ちなみに、女性医学の分野で、このテーマで研究している先生は少ないんですよね。よく研究されているのは骨粗鬆症や高脂血症。糖代謝は、マニアックといえば、マニアック(笑)。
田中:鮫島先生は、糖代謝を研究していたことで、役立ったことってありますか?
鮫島:例えば、この研究をしていなかったら、新しい糖尿病薬のことも知らなかった。産婦人科だったら処方しないような薬についての知識がつきました。
一度失敗すると、3ヶ月が無駄になる?
ー研究の大変さって、どういうところ?
鮫島:行き詰まることは、よくあるよね。綺麗なデータが欲しくても、なかなかうまくいかない。データのバラツキが大きかったりすると、棄却検定をすればいいけれど。
田中:棄却検定が繰り返されて、どんどん見栄えが良くなると、今度はデータとして本当に正しいかどうか、怪しくなるという(笑)。
鮫島:結局、そのデータが本物かどうかは、本人にしかわからない。あったデータをなかったことにしてしまえば、証拠は残らないわけだから。本人の倫理が問われますよ、これは。
鮫島:データの改ざんだって、結果を出すことが常に求められるプレッシャーから起きてしまったんでしょうけど。
田中:でも、ああいう発表をしたら、みんな同じ研究をするから、あれ?結果でないじゃん?って、すぐ分かりますよね。
鮫島:他に仕事があると、研究がうまくいっていなくても、やり過ごせるけれど。研究一本だと苦しいよね。大学院も後半になってくると、卒業が控えているから、つい綺麗なデータが欲しくなっちゃう。
田中:研究者も人の子ですから、良からぬことが、よぎってしまうことも・・・(笑)。もちろん、やりませんけど。
鮫島:私の場合、やり方を変えてみたらなんとかなって、捏造までしなくてすみましたけど(笑)。


田中:そもそも私たちの実験が、マウスを3ヶ月育ててから始まるので、一度実験を失敗したら、3ヶ月間がすべて無駄になるという。
鮫島:失敗しても、また次のマウス買えばいいや、というわけにはいかないから、もうドキドキですよ。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月で解剖するんですけど、3ヶ月目で思いっきり失敗したことがありました。
田中:ちなみに、どんな原因で?
鮫島:細胞が生きている状態で処理をして、細胞を染めて、それをフローサイトメトリーで流して見るんですけど。翌朝、細胞の処理がうまくできてなかったんですよ。薬学部の学生たちにも手伝ってもらっていたんだけど、その人たちにも申し訳なかった。みんな、「私かもしれません」「いや、私かもしれません」ってオロオロして。
田中:その状況、目に浮かびます(笑)。買ってきたマウスをその日に解剖して解析するならいいけれど、この研究はそれが出来ないし。簡単にリカバー出来ませんよね。
鮫島:このテーマをやる限りは、ついて回るよね。マウスと長い付き合いになるので、必然的にみんな愛護的になります(笑)。
異色のコラボ、生まれています。
ー富山大学病院だからできることってありますか?
鮫島:コラボはしやすいのかなと思いますね。産婦人科じゃない先生と相談しやすかったり。小さいところなので、だいたいみんな顔見知りになって。ちょっと聞きたいことがあった時、例えば免疫学の先生からアドバイス欲しいなって思った時に、聞きやすかったり。
田中:漢方も多いですよね。婦人科の患者さんには、漢方の処方をすることも多いですけど、漢方の専門医にも相談しやすいですしね。
鮫島:いまちょっと個人的に関心があるのは、未病なんですけど。未病というのは、早めに介入して、病気になる前に予防するっていう考え方で、漢方学的な考え方なので、そういう専門の先生たちに相談しやすいんですよね。いまちょうど、未病の研究を他の先生と進めているところ。更年期になってからの、体の変化の原因遺伝子を探したりしています。
田中:未病プロジェクトは結構な密度ですよね。漢方の先生とか、薬学の先生のほかに、五福キャンパスの工学部の先生とか、東大の数学の先生とか、すごいコラボ数。
鮫島:未病は今、教授お気に入りのテーマかと(笑)。一つの研究室で思いつくアイデアってもう限界が来ていて、複数の人たちと同じデータを見ると、全然違うものが見えて来たりするので。逆に、婦人科のアドバイスが欲しいって、他の先生から、声がかかることもありますね。
ーふだん、臨床ではどんな患者さんを診ていますか?
鮫島:女性医学って、今注目されている分野だと思うんですよ。でも、まだあまり認知されている感じもないなあ。
田中:更年期障害や不定愁訴などの従来の患者さんの他にも、漢方外来や、女性アスリート外来の患者さんもみてますよね?
鮫島:長距離選手は長い間無月経になって、疲労骨折のリスクが高まったり、生理痛によってコンディションの波が出やすかったり。そのあたりをピルを使って抑えてあげたり、体調管理面のアドバイスをしています。
田中:漢方外来も、やりがいがありそうです。患者さん、多いですよね?
鮫島:多いね。喋るだけ喋って、じゃ、いつもと同じ薬で!といって終わったり。これはもはや、医療なのか、なんなのか(笑)。
田中:患者さん、鮫島さんのファン多そうだなあ。
鮫島:午前中の外来は時間との戦いなんですが、午後は比較的余裕があるので、患者さんの話を長めに聞いたりして。もっぱらプライベートのことですね。ご家庭のことや旦那さんのこと。点数はつかないですけど(笑)。よく患者さんには、「私の話で使えるところあったら、ぜひ使ってください」なんて言われたりして。
田中:それはそれで面白いですね(笑)。
鮫島:ただ、一つのことだけをやっているよりも、いいのかなという気がします。私の場合は、水曜と金曜が外来で、火曜と木曜が手術。それ以外が研究です。臨床一筋ではないからこそ、常に新鮮な気持ち、新しい発想で医療に臨めるのかなと思いますね。
田中:それはよくわかります。私は今、大学院2年生ですが、学生視点にもう一度立ってみたことで、また新たな発見があったり。
鮫島:大学院で研究をすると、これまでやっていた治療もまた違って見えてきますよね。それに、ずっと同じことを続けると、人間どうしても飽きがくる。臨床だけでなく、研究を続けることで、視野も広がるし、得られる情報も多いし。私も、院を卒業した今でも、研究は続けています。
