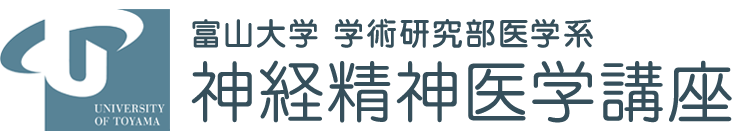令和6年6月1日付で富山大学神経精神医学講座教授を拝命しました髙橋 努です。私は平成8年に本学(3大学合併前の富山医科薬科大学)を卒業し、当時の倉知正佳教授が主催する当講座に入局しました。その当時からの講座の変わらぬ目標として「地域医療で活躍する人材の育成と精神医学の重要疾患に対する総合的な研究の推進」が掲げられています。私自身、学生や若手医師の教育に加え、地域に根ざした臨床活動と国際水準の研究の両立を目指して取り組んで参りました。今後とも講座の良き伝統を継承し、さらに発展させることを目指していく所存です。
以下に、当講座の特徴や方針を簡単にご紹介します。
1.臨床―精神科疾患の早期診断・早期治療の推進
基本方針として「精神科疾患の早期診断・早期治療の推進」を掲げています。精神科疾患には慢性的経過を辿るものが多いのですが、私たちは前駆期や初発期の診断・治療を特に重視し、その充実によって長期転帰を改善させることを目標としています。また当然ながら、地域精神科医療への貢献を重視して活動しています。当科の診療対象は、統合失調症、気分症、神経発達症、ストレス関連症群、摂食症群、認知症、睡眠障害などの精神科疾患に加え、性別不合や高度肥満など多岐に渡り、いずれも重要なものばかりです。これからは精神科診療における早期診断・早期治療センターとして、医療機関や関係諸機関とも連携し、地域の中で十分に機能を発揮できることが重要と考えています。
2.教育―地域で活躍する専門医の養成
富山県内の多くの精神科医療機関や公的機関で当講座出身の医師が活躍しています。今後も地域医療に貢献できる優秀な精神科医を育てていくことが当講座の大きな役割です。本学附属病院が基幹施設となる精神科専門医研修プログラムでは地域における考えうるリソースを集結して専攻医の指導体制を構築しており、また児童青年期精神医学を志す専攻医向けには、本学附属病院こどものこころと発達診療学講座(辻井農亜教授)との連携研修を行なっています。研究を行うことは臨床医としての将来にも有益であり、若手医師の大学院進学やその後の海外研究留学も大いに奨励しています。
3.研究―重要疾患の解明と客観的診断法と早期治療法の開発
主として生物学的精神医学の立場から、精神科領域における重要疾患の病態解明や診断・治療の進歩につながる実証的な臨床的および基礎的研究を推進しています。第一のターゲットは統合失調症であり、脳画像、神経薬理、神経生理、認知機能、遺伝子、動物モデルなどを用いた多角的アプローチによる病態研究や、先進的な早期介入研究・活動を実践しています。国内および国際共同研究も積極的に行っており、当講座は当該領域における臨床・研究の拠点として世界的に認知されるに至っています。今後さらに研究が深まるとともに、研究領域の幅も広がることを期待しています。
最後になりますが、今後の講座の発展のためには、未来を拓く若い力が不可欠です。本年4月より「医師の働き方改革」が施行されましたが、当講座ではそれに先立ち、医局員のワークライフバランスや女性医師の働きやすさを考慮した講座運営を行なってきました。育児中の女性医師の当直や夜間オンコールの免除、男性医師の育児休業取得、健康上の理由による短時間勤務導入などにより、多様な人材が互いに協力しながら活躍する環境が整っています。そのような中、各医局員がモチベーションを持ってそれぞれの目標に向かって取り組んでおり、今後さらに多くの新しい仲間が当講座に加わってくれることに期待しています。
令和6年6月
髙橋 努