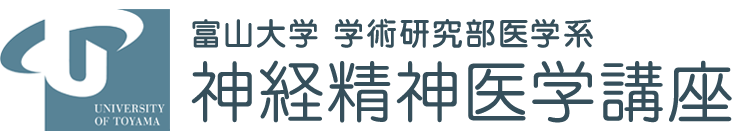初期臨床研修
はじめに
2020年度に医師臨床研修指導ガイドラインが改訂されました。この改訂により、精神科は選択必修科目から必修科目へと変更されました。研修内容は精神科専門外来や精神科リエゾンチームでの研修を含むことが必須となっており、また急性期入院患者の診療を行うことが望ましいとされています。当科ではこれらの経験を積むことができる環境が整っています。
精神科研修で経験したことは、これから進む診療科の臨床現場で必ず役に立つと思います。精神的苦痛を持った患者さんからどのように話を聴けばよいのか、どんな声かけをしたよいのか、どういうタイミングで向精神薬を使うのか等、一緒に考えながら診療をしていきましょう。
到達目標
1か月の研修期間、2〜3か月の研修期間において以下のような到達目標を作っています。進みたい診療科が決まっている場合には、独自の目標(例えば、外科に進む場合に、「術後せん妄の対応ができる」等)を作ってもよいと思います。指導医にご相談ください。
到達目標(1カ月)
- 系統的な診断面接に基づき、国際診断基準に準拠した診断を行い、治療計画を立案することができる。
- 神経学的検査、心理学的検査、脳画像検査、脳波などの諸検査を実施し、解釈できる。
- 向精神薬についての基本的知識を持ち、適切に使用できる。
- 診療を通じて、他職種と協調したチーム医療ができる。
- 身体療法の一つとして、電気けいれん療法(ECT)を経験する。
患者さんとの会話や関わりの中から学ぶという姿勢を大切にしてください。
到達目標(2~3カ月)
- 精神疾患の回復過程に応じた療養指導や薬物療法を行うことができる。
2~3か月の研修の場合には、精神疾患の急性期から回復期に至るまでの経過をより詳しく診ることができます。例えば、うつ病の回復には2、3か月程かかることも多く、1か月では経験できない患者さんの変化をみることができます。

<病棟チームカンファレンス>
研修内容
病棟チームの一員として入院患者さんの担当をします。また外来診療では、初めて来られる患者さんの予診(病歴聴取)を担当し、その後の本診察の診察補助を行います。研修の終わり頃に症例検討を行うため、資料作成やプレゼンテーションなどの経験を積むことができます。
魅力ある研修内容
- 病棟診療はチーム制をとっており、3~4人で構成するチームの一員として診療を行います。チームカンファレンスを毎週行い、診断的検討をしたり、治療方針を共有します。
- 研修医が単独でも施行可能な検査(抑うつ評価尺度、簡易認知機能検査など)を習得できるよう指導します。
- 脳波、脳画像(MRI、SPECT)の判読、ならびに向精神薬(抗うつ薬、抗精神病薬、睡眠薬など)の使用の基礎が理解できるように指導します。
- 症例検討会のために資料作成やプレゼンテーションの仕方などを指導します。
研修担当者より一言
将来の志望する科がはっきりしている場合、その科に関連する病態の患者さんを担当してもらうなどの配慮もしますので、希望があれば伝えてください。

<病棟回診前のカンファレンス>
研修スケジュール
午前中は、外来の初診患者さんの予診を担当してもらいます。その他の時間は病棟の担当患者さんの診療にあたってもらいます。週に1回、教授回診とチームカンファレンスがありますので、担当患者さんのプレゼンテーションをしてください。その他の業務内容について以下の図を参照してください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 |
外来業務 (予診、初診陪診) |
外来業務 (予診、初診陪診) |
外来業務 (予診、初診陪診) |
外来業務 (予診、初診陪診) |
外来業務 (予診、初診陪診) |
| 午 後 |
病棟研修 | 教授回診 医局会 |
病棟研修 | 病棟研修 | 病棟研修 |
外来業務
- 初診患者の予診(病歴聴取)
- ベシュライバー(診察のカルテ記載)として初診に陪席
病棟業務
- 入院患者の受け持ち
- 病棟行事やSST(Social Skills Training)
医局会
- 受け持ち患者の症例検討
その他、興味があればカンファレンス・勉強会(認知症症例検討会、古典を読む会など)にも参加できます。
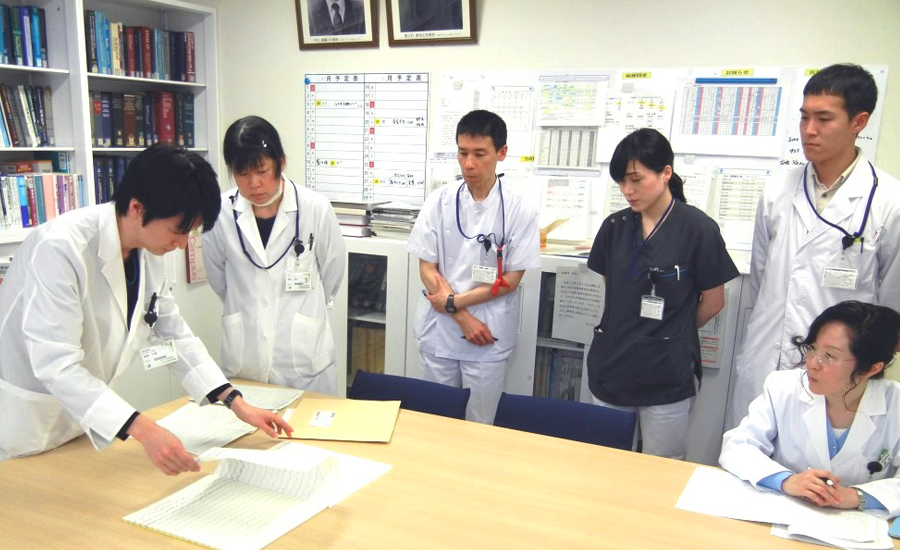
<症例検討会にてプレゼンテーション>