
ホーム > 周産期部門(産科・新生児科) > 妊娠高血圧症候群
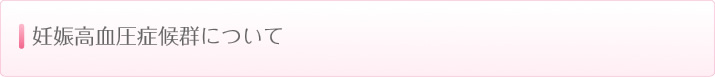
2005年4月から、「妊娠中毒症」から「妊娠高血圧症候群」へと名称が変わりました。
皆さんは昔から言われている「妊娠中毒症」に慣れていらっしゃるので、「妊娠高血圧症候群」という呼び方には違和感があると思います。
まずは、馴染みのある「妊娠中毒症」について、次に新しい概念である「妊娠高血圧症候群」について簡単にお話したいと思います。
妊娠中毒症とは?
血圧が高い(高血圧)、蛋白がおりる(蛋白尿)、むくむ(浮腫)の3つのうちどれかががあれば、妊娠中毒症と呼んでいました。
また最も症状がひどくなると、妊娠中の痙攣(子癇(しかん))を来たし、お母さん・赤ちゃんとも生命の危機的状況になります。
これら子癇・高血圧・蛋白尿・浮腫は妊娠が終了することで軽快することから、胎児や胎盤から毒性物質が出て母体に異常をきたすと考えられてきました。それで「妊娠中毒症」という名前がつけられました。

「妊娠高血圧症候群」と名前が変わった理由は?
「妊娠中毒症」の研究が進むにつれ、血管の一番内側にある細胞(血管内皮)が傷つき、さらに血液が固まりやすくなっている状態になっていることがわかってきました。また私たちの教室の成績により、赤ちゃんに対する拒絶反応が起こっていることも明らかになってきました。高血圧が「妊娠中毒症」の主体であるとの考えより、「妊娠高血圧症候群」へと変更することが決まりました。
変更点を簡単に言いますと、次のようになります。
- 尿に蛋白が認められたり、むくみを認められるけれども、血圧が高くない場合には、妊娠高血圧症候群とは呼びません。
- 妊娠中(20週以降)に血圧が上昇し、分娩後(12週まで)に正常値に戻る場合には、「妊娠高血圧」と呼びます。具体的には収縮期血圧が140mmHg異常、拡張期血圧が90mmHg以上です。
- 血圧が高く、さらに尿に蛋白が認められる場合には、「妊娠高血圧腎症」と呼び、厳重な管理が必要です。
妊娠中のむくみは重要でなくなったのでしょうか?
「むくみ」は全妊婦さんの30~80%に認められるので、「むくみ」があるからといって特別な意味はありません。
また「むくみ」があってもなくても赤ちゃんには影響しないこともわかってきました。
そのために「むくみ」は「妊娠高血圧症候群」の症状からは外されました。
子癇発作とは?
妊娠20週以降に初めて痙攣(けいれん)発作を起こしたもののうち、「てんかん」や二次性痙攣が否定されたものをいいます。
昔はよく見られましたが、最近では血圧の管理がいいためか、ほとんど見かけることはなくなりました。
しかしながら、「妊娠高血圧症候群」に頭が痛い・めまいがする・目がちかちかする・まぶしい感じがする・胃が痛む・吐き気がする・吐くなどの症状が起こった場合には、子癇発作の前兆であることがあるので、注意が必要です。
妊娠高血圧症候群の予防は?
妊娠中に塩分を摂取しすぎたり、食事を食べ過ぎたりして体重が多くなりすぎると、妊娠高血圧症候群が発生しやすくなります。このため妊娠中の食事管理は大切です。
塩分は1日8-10gをめどに、またあまり食べ過ぎず、良質の蛋白質を摂取してください。
ただし、これらの予防をしていても、特に初めての妊娠の際に、妊娠高血圧症候群が発生することがあります。これはお父さんの体質に対して、お母さんの免疫担当細胞(防御機構)が過剰に反応し、赤ちゃんを拒絶している現象とも考えられます。
妊娠高血圧症候群の治療は?
1. 安静療法+食事療法
安静にすると血圧も下がり、胎盤へ行く血液の量も増え、赤ちゃんにとっても好都合です。食事療法は1800kcal、塩分8gをめどに摂取すると良いでしょう。
2. マグネシウム療法
子癇発症予防のため、マグネシウム製剤を投与することがあります。特に重症例では投与することが多くなります。
3. 降圧剤
血圧が高いからといって血圧を急激に下げると、赤ちゃんへ行く血液の量が減ってしまい、急速に赤ちゃんの状況が悪化します。そのため徐々に血圧を下げていき、140/90mmHgくらいとなるように血圧を調節します。
4. 分娩(妊娠の終了)
あまり血圧が高くなりすぎると母児ともに危険ですので、早産であっても帝王切開で赤ちゃんを分娩させることがあります。このほうがお母さん、赤ちゃんにとってよい結果となります。この判断が難しいのですが、当科では専門の産科医も常駐していますし、新生児の専門医もいますので安心していただけると思います。





