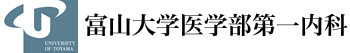臨床研修カリキュラムについて
 糖尿病・代謝・内分泌内科では、糖尿病専門医、内分泌専門医を中心にして、糖尿病、甲状腺疾患や、副甲状腺、副腎、下垂体疾患、脂質異常症、肥満症などの代謝・内分泌疾患全般の診療を行っています。
糖尿病・代謝・内分泌内科では、糖尿病専門医、内分泌専門医を中心にして、糖尿病、甲状腺疾患や、副甲状腺、副腎、下垂体疾患、脂質異常症、肥満症などの代謝・内分泌疾患全般の診療を行っています。
糖尿病診療に関しては、食事・運動療法の指導や、薬物療法、強化インスリン療法などによる血糖コントロールの改善だけでなく、血管合併症、脂質異常症や高血圧の併発にも注意をはらい、動脈硬化症の進行阻止をめざして、包括的に質の高い診療を行っています。
また、内分泌疾患に関しては、その代表的疾患である甲状腺疾患を中心に専門外来を行っており、バセドウ病、慢性甲状腺炎、甲状腺腫瘍性疾患の診断・治療のため、採血検査、画像診断(超音波検査、シンチ検査、CT・MRl検査など)の他に穿刺吸引細胞診を行い、診療の質の向上を図っており、さらにこれまで、貴重な内分泌疾患の症例報告を行い、実績を積み重ねてきています。
以上のような背景から、当科の研修カリキュラムは、代謝・内分泌疾患を全身疾患としてとらえ、その病態を的確に把握し管理・治療することができる臨床知識・技能の修得をめざし、地域医療に貢献できる優れた糖尿病専門医・内分泌専門医の育成を目的としています。
研修内容と到達目標
1,2年目(初期研修)
富山大学附属病院の研修システムに基づき初期臨床研修を行います。3年目以降(後期研修)
専門医研修のため、日本糖尿病学会および日本内分泌学会に入会することを原則とします。指導医は、少なくとも以下に示す項目を達成できるよう後期研修医を指導します。また、後期研修医は、管理栄養士による院内食事箋の指導もうけます。病棟では週1回内分泌糖尿病カンファランス(症例検討、抄読会、セミナーなど)を行っており、受け持ち症例に関して他の指導医からも指導をうけます。
また、少なくとも年1回の学会発表、または論文発表が可能なように指導医から適切な指導をうけます。その他、糖尿病教室での集団指導を担当します。
【達成目標】
- 糖負荷試験によるインスリン分泌能・インスリン抵抗性の評価ができる。
- 糖尿病の病型分類について説明できる。
- 糖尿病性慢性合併症の評価ができる。
- 糖尿病性(高血糖性)昏睡の治療ができる。
- 個々の生活環境を考慮した糖尿病の食事療法と運動療法の指導ができる。
- 個々の病態を考慮した糖尿病の薬物療法が選択できる。
- 患者の病態と生活状況を考慮したインスリン療法を実施できる。
- 糖尿病の患者教育(糖尿病教室など)に参画できる。
- 患者の理解度や心理状態に配慮した治療法を選択できる。
- メタボリックシンドロームの診断と治療ができる。
- 肥満(単純性肥満及び内分泌性肥満)の鑑別診断と生活指導および治療が適切に行える。
- 低血糖(インスリノーマ等)の鑑別診断と治療ができる。
- 主要な内分泌疾患を列挙できる。
- 各種負荷試験を用いたホルモン動態の評価ができる。
- 甲状腺、副腎や下垂体ホルモン異常の鑑別診断について説明できる。
- 内分泌性緊急症(急性副腎不全、甲状腺クリーゼ等)への適切な対応ができる。
- 適切なホルモン補充療法と療養指導ができる。
- 内分泌疾患におけるシンチグラム、血管造影、静脈サンプリングの所見について説明できる。
- 骨粗鬆症の診断、治療及び予防が適切に行える。
週間スケジュール
火曜日 教授回診
木曜日 糖尿病、代謝・内分泌カンファレンス
研修指導・評価は、日本糖尿病学会認定指導医、日本内分泌学会認定内分泌代謝科指導医が行います。
木曜日 糖尿病、代謝・内分泌カンファレンス
研修指導・評価は、日本糖尿病学会認定指導医、日本内分泌学会認定内分泌代謝科指導医が行います。