肝臓疾患の診療
肝臓疾患
急性肝炎の原因と治療
急性肝炎・急性肝障害には肝炎ウイルス(A型、B型、C型、E型など)、自己免疫性、薬物性などの原因によるものや、原因不明のものもみられます。
こうした肝障害の多くは自然に軽快しますが、中には重篤化し、様々な臓器合併症や肝不全にいたるものもみられます。
当科では可能な限り原因を明らかにし、適切な治療を目指しています。そのため積極的に肝組織生検検査も行い、
免疫組織化学的手法なども用いて原因の検索を行っています。
出血傾向や腹水などにより通常の経皮的肝生検が行えない場合は経頚静脈的肝生検も放射線科と共同して行っております。
B型肝炎、C型肝炎はウイルスの同定とその増殖メカニズムが明らかとされたことから新規の治療薬が開発されており、積極的に治療導入を行っています。
重症例に対しては血漿交換療法を含めた集学的治療を行い、肝移植への橋渡し治療を行い、治療成績の向上を目指しています。
慢性肝炎の治療
本邦における慢性肝炎の最大の原因であったC型肝炎ウイルスは、これまで1年以上のインターフェロン治療でも半数程度しかウイルス排除ができませんでしたが、
今や最短8週間の1日1回の内服(直接作用型抗ウイルス薬:Direct-Acting Antiviral (DAA)でウイルス排除がほとんどの患者さんで可能となりました。
当科では積極的にDAA治療を行いその効果を検討しています。
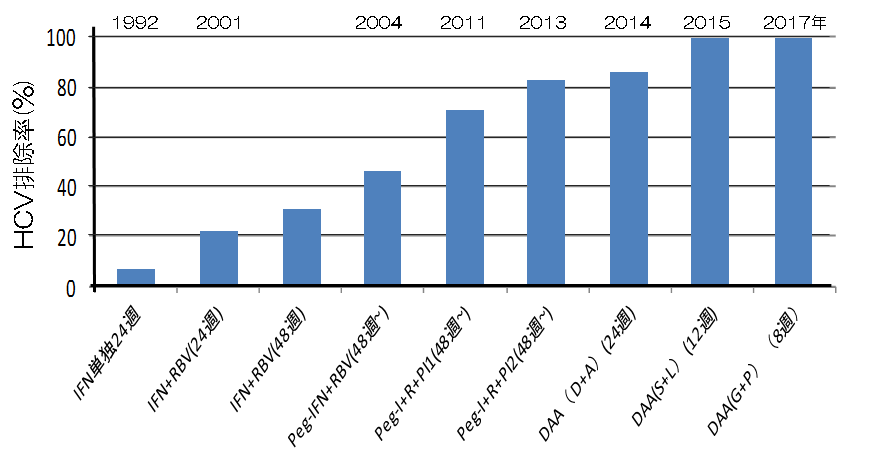
また本邦を含むアジア地域に多く患者がみられるB型肝炎ウイルス感染に対しては、肝疾患の進行の程度や肝炎の状況を把握し、
適切に治療(核酸アナログ治療)を行っております。
若年者においてはインターフェロン治療を含めた核酸アナログシ―クエンシャル療法などの適応も検討しています。
自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎なども肝組織生検結果をもとに確実な診断を目指し、診断に基づいた治療を行っています。
肝硬変の治療
肝臓は沈黙の臓器といわれるように自覚症状に乏しく、肝硬変の状態で発見されることも多くあります。
肝硬変への進行自体も自・他覚所見に乏しく発見困難な場合もあります。
当科では、肝組織生検検査に加え、様々な血液マーカーやエコーなどを用いた非侵襲的診断法でその進行度を診断し、適切に治療介入を行っています。
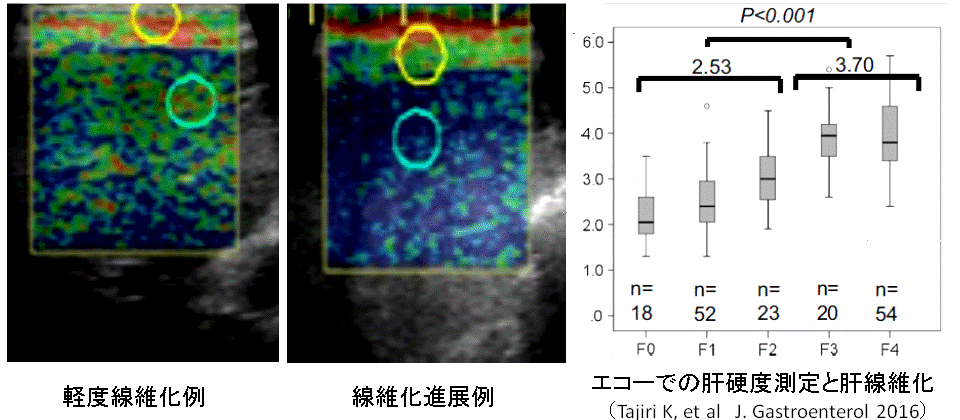
肝硬変が非代償化すると腹水、肝性脳症、消化管出血など様々な重篤な症状を呈することがありますが、新規治療薬を積極的に用いて治療成績の向上を図っています。
また肝硬変は脳、肺、心臓、腎臓、腸管、筋肉、精神など全身(心)に及ぶ病態であり、トータルマネジメントを目標に治療を行っています。
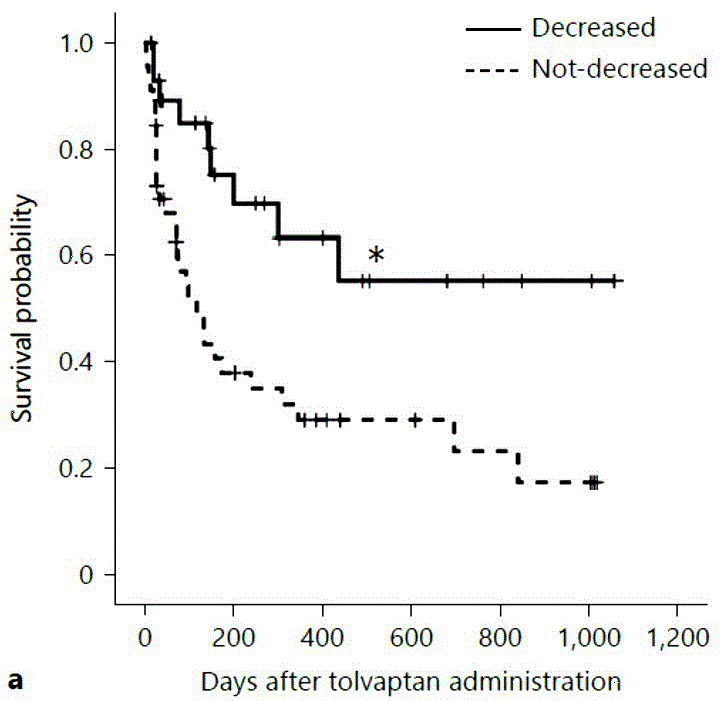
↑難治性腹水治療における既存の利尿剤の減量による生存への効果
出典: Tajiri, et al. Dig Dis 2018
1例1例に対して丁寧に、そして最善の治療法を行うことを目標としており、その良好な治療成績を学会や論文で報告しています。
肝癌の治療について
肝臓にできるがんの90%は肝細胞癌で、その他肝内胆管癌、混合型肝癌、神経内分泌癌、リンパ腫、転移性肝癌などがみられます。当科では、外科、放射線科との毎週の合同カンファレンスを行い、 個々の症例に対し最適な治療方針を決定しています。
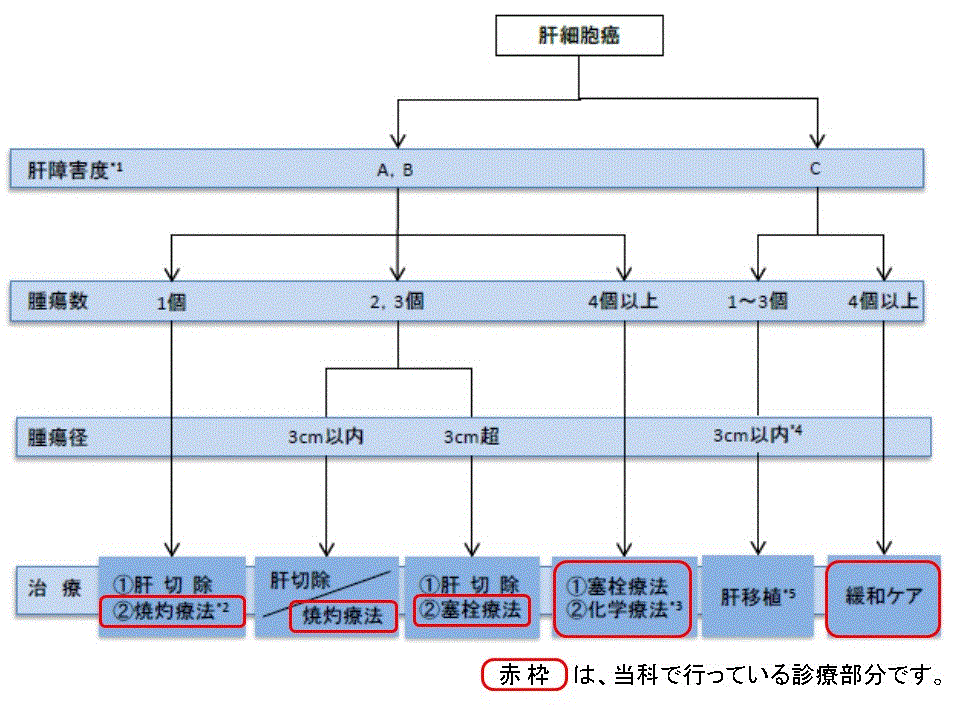
患者様一人ひとりに対して丁寧に、そして最善の治療法を行うことを目標としており、その良好な治療成績を学会や論文で報告しています。
ラジオ波焼灼療法について
ラジオ波焼灼療法(RFA; radiofrequency ablation)は、経皮的(症例によっては腹腔鏡下、開腹下)に電極を病巣に挿入し、電極周囲を460KHzのラジオ波により誘電加熱し、癌を壊死に陥らせる方法です。
1回の焼灼で約3cmの範囲の壊死効果が期待でき、アルコール注入療法などに比べ、はるかに容易にそして確実に病変を治療できることから、現在では肝癌局所治療の中心となっています。
2004年4月から保険収載され全国で広く使用されるようになりましたが、当科では保険収載前の2000年よりRFAを導入しており、肝細胞癌、転移性肝癌に対し積極的にRFAを施行しております。
年間60~100例の症例にRFAを実施しており、県内トップの実績があります。病変の検出・同定の際には造影エコー法やCT/MRI画像をもとにしたV-naviシステム、さらにはCT/MRI画像をデータ解析した仮想超音波像を使用し、
より確実な病変の検出を図っており、基本的には肝臓内すべての病変が対象となります。
治療に際しては、通常のエコーで描出不良な病変や消化管など他臓器に接した病変に対しては人工胸水・腹水を作成した上で、より安全で確実なRFAを施行しております。
さらに、血管近傍の病変などに対しては肝動脈カテーテルを用いた肝動脈化学塞栓療法を併用し、治療効果の向上を図っています。また3㎝をこえる大型の病変に対しても、
同時に複数本の電極を穿刺したりすることで積極的に治療を行っています。
治療の実際: 横隔膜下の3㎝を超える病変の治療例です。
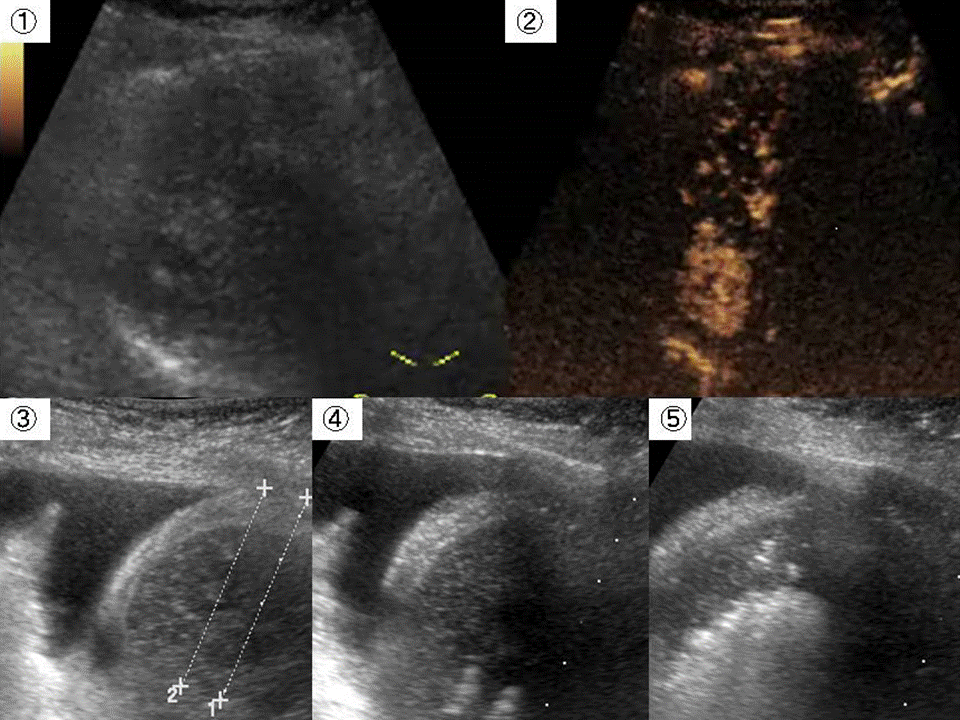
- ①人工胸水を使用して病変がみえてきますが、肝硬変もあり描出は不明瞭です。
- ②ソナゾイド造影エコーを行うと病変がはっきり確認できます。
- ③人工胸水を通過し最終プランニングを行います。
- ④複数本RFA針を穿刺します(この場合は3本穿刺)。
- ⑤焼灼を行ったあと(通常10分以内に終了)
塞栓療法について
肝臓は肝動脈と門脈の2重支配となっている特殊な臓器であり、肝動脈塞栓療法が可能です。この方法は多発肝細胞癌では世界的に広く行われています。
細経のマイクロカテーテルを病変近傍の栄養血管まで誘導し、リピオドール(油性造影剤)と抗癌剤を混和した薬液とゼラチンなどの塞栓物質を用いて治療します。
当科では通常の方法で効果が乏しい場合や肝予備能が不良な場合には、薬剤溶出性の球状塞栓物質(新規の塞栓物質)を用いたり、
バルーン閉塞し薬物を選択的に腫瘍内に注入したりすることで治療効果の改善を図っており、 その成績を論文報告しています(Kobayashi S, Tajiri K, et al, J Hepatocell Carcinoma 2020)。
こうした血管治療は放射線科に依頼する消化器内科も多いですが、当科では自科中心で治療を行っており、患者さんの個々の病態、疾患背景を考慮した治療を行っています。
肝がんの化学療法
肝がんは他臓器の癌に比べ、化学療法抵抗性が強く、また慢性肝疾患を背景に発症することから肝臓の機能が低下していることが多く、全身化学療法の成績は極めて不良でした。
分子標的薬が進行肝細胞癌に対して初めて生存延長のエビデンスを示し、2009年から使用可能となりました。
近年さらに複数の分子標的薬が登場し、2020年から免疫チェックポイント阻害剤も使用可能となりました。
当科では治療成績の更なる改善を目指し、分子標的薬と他の治療法を組み合わせた集学的治療を行っており、その優れた治療効果を論文報告しています(Tajiri K, et al. Onco Targets Ther 2019)。治療効果によっては切除やRFAを組み合わせたコンバージョン治療を行い、治癒を目指します。
また肝胆膵グループとしてJCOGなどの全国臨床研究グループに参画し、治療の標準化や最新治療法の導入も行っています。